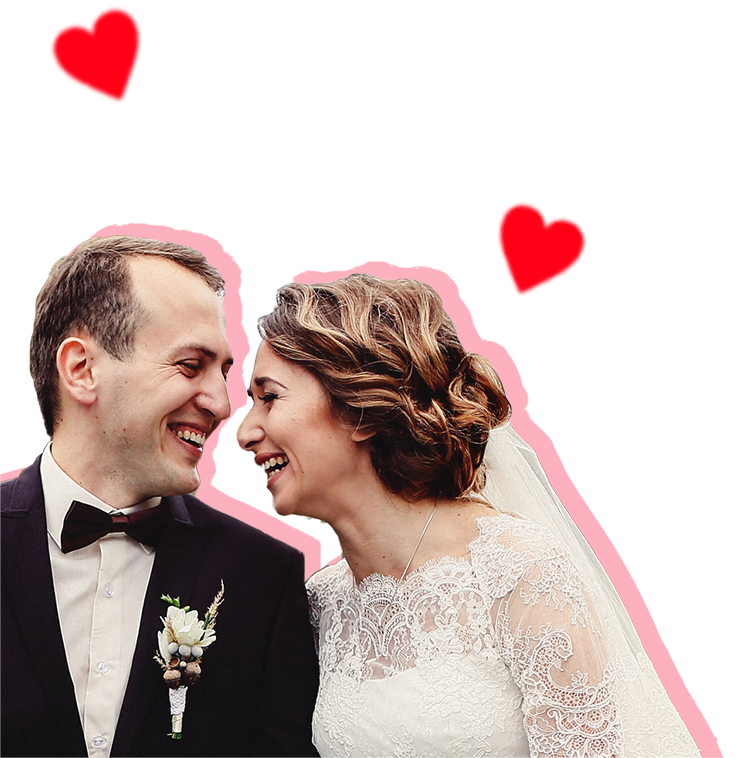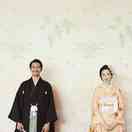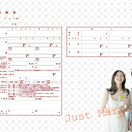最近ある俳優の不倫問題が、夫婦ともに有名な俳優ということもありワイドショーの格好のネタとなっています。今回この俳優の不倫がなぜこれほど、とくに子どものいる女性たちの怒りをかっているのか、他人の夫婦関係に関心が集まっているのか。それはその俳優の妻が妊娠中と産後、さらには双子の乳児を育てていた期間に不倫していた、というのが大きな理由になっています。
夫の「無知」が夫婦関係を壊す ―産後うつ、産後クライシス、産後の性生活…夫が知っておくべき産後の妻についての「知識」

無知な夫の発言が、妻を、そして夫婦関係を傷つける
女性は妊娠、出産において身体が大きく変わっていき、とくに産後の母体のダメージは「交通事故に遭うのと同じ」と例えられることもあります。しかしこの変化について経験することがないので分からない上に想像が及ばない夫もいるようです。ひどい場合には、妊娠中のつわりやお腹の張り、腰痛など体調が悪いのにも関わらず、「病気じゃないんでしょ」「俺の夕ご飯は?」と言うような夫もいるのだとか。家事全般を自分一人がやっていてすごくつらかったという妻の経験談は多く聞かれます。
身体の変化は出産したあとにも続きます。産後6週間を「産褥期(さんじょくき)」といいますが、これは出産で疲労した体を休める時期になります。この産褥期から数か月か1年の間、赤ちゃんの世話は授乳や沐浴、おむつ替えや離乳食、ときには予防接種や健診と目まぐるしい日々が続きます。赤ちゃんのお腹を満たし、着替えさせ、自分も身支度をして、買い物のために外出する準備だけでも数分では済みません。日常の家事をしながら、もし上の子がいればそちらのケアもしなければなりません。
産後から乳児期は、赤ちゃんは可愛く、たくさんの幸せを感じる反面、子育て期全般を通じてもっとも負担が大きい時期でもあります。人手はいくらあってもいいほどで、夫は妻の心身を労りながら、母親ができる授乳以外の沐浴やおむつ替え、ミルクや上の子の世話などをし、夫婦が全力で取り組まざるを得ない毎日なのです。
しかし男性はなかなか親になる実感が持ちにくい、妻や赤ちゃんに対して何をどうしたらいいのか分からない、と戸惑う人も多いようです。今回は夫が最低限知っておきたい産後の妻の体と心の変化についてご紹介します。
1. 産後は「ホルモンのせい」で精神的に不安定になる
「マタニティブルーズ」とは、分娩直後から産後7日~10日以内にみられる精神的な不調です。妊婦から、出産、授乳とたどる母体はこの時期、体内で赤ちゃんをはぐくむ体から母乳を与える体へと変化する必要があるため、劇的にホルモンバランスが変化します。そのことにより、精神的に不調をきたしやすいといわれています。おまけに産後の身体のダメージや、生活の変化、母としての責任感の重さからくるストレスなども相まって、理性ではコントロールしにくいほどに心が不安定になる時期なのです。落ち込み、頭痛、涙が止まらない、不眠、イライラ、食欲低下などがみられます。これは多くの女性が産後に経験することで一過性のものです。
この時期は夫こそ、理性的でいるように心がけましょう。妻の精神不安は妻のせいではなく、夫のせいでもなく、「ホルモンのせいであること」、「一過性であること」、などを念頭に、妻の思いに耳を傾けて、代わってできることやサポートをし、少しでも妻が休めるように心がけましょう。
精神的な不調の症状が長期間続くと「産後うつ」の可能性もあります。夫は不安や不満をぶつけられたり、強くあたられるなどつらい場面もあるかもしれません。マタニティブルーズや産後うつの知識がないと、なぜこのような精神状況なのか客観的に分からないまま二人ともどんどんつらくなっていきます。しかし「妻のせいでもなく、夫のせいでもなく、ホルモンバランスの変化せいだ」とあらかじめ知っているだけで、お互いに気持ちが少しは軽くなり、なんとかやり過ごせることが多いのも事実です。ただし、つらいとき、不安や不眠が強い場合には、市区町村の運営する保健センターや医療機関に早めに相談をするようにしましょう。記事の最後に相談先をまとめましたのでご参照ください。
2. 母体に起こる様々な身体的トラブル
赤ちゃんが母乳を吸うことによってオキシトシンというホルモンが出ます。このホルモンは子宮を収縮させる効果があり、母体の回復を促す効果があります。しかし母乳をあげていると、乳腺に母乳がたまり、そこに細菌が入りこんで乳腺炎になることがあります。胸が熱をもったり、赤くはれたりして、非常に痛くなり発熱することもあります。症状が軽いうちに医療機関にて受診すべきところです。
また、母乳をあげる際に赤ちゃんに吸われる刺激や赤ちゃんの歯で噛まれることで乳頭がひび割れたり切れたりします。これを乳頭亀裂といいます。飲ませ続けているうちに乳頭が丈夫になり自然に治ることもありますが、非常に痛くなることもあります。このような場合は医療機関を受診して適切な処置を講じるべきです。母乳関係のトラブルはたくさんのお母さんが経験することですが、乳頭亀裂がおきるとあまりに痛く赤ちゃんに母乳をあげる時間をつらいと感じることもあります。
また産後、お産の際にきばったことにより脱肛してしまうことがあります。医療機関を受診する必要があります。
その他、骨盤底筋群が伸びきって弱ってしまうために起こる尿漏れ、産後脱毛、膀胱炎、恥骨・尾てい骨の痛み、頭痛、便秘、腰痛、赤ちゃんを抱っこして腕にかかる負担から腱鞘炎(けんしょうえん)なども起こりえます。こうした体のトラブルは、そのままにしておくと入院するほど悪化したり、10年後、20年後の年をとったときに症状が現れることもあります。
3. 産後の性生活
産後の性生活の再開の目安は、一般的に「一か月健診で医師から体の回復が確認されたあと」になります。具体的には会陰切開の傷が治り、悪露(おろ:産後子宮の中や膣の傷から出る血液を含む分泌物)が出なくなった後ということです。会陰部は十分に伸びきらないまま出産時に裂けてしまうことがあります(会陰裂傷)。会陰裂傷を避けるために、はじめから会陰部を切り(会陰切開)赤ちゃんが出やすいようにすることもあります。いずれの場合にも赤ちゃんが出た後に会陰部を縫合しますが、産院ではドーナツ型の椅子に座ったりしますが傷はしばらく痛みます。
一か月健診でOKが出たとしても、一か月でもとの性生活に戻る夫婦は少ないでしょう。出産の疲労がなかなか取れない、上記のように会陰切開した場所がまだ痛い、母乳をあげている間は排卵を抑制するホルモンが分泌される、2、3時間おきに起きる赤ちゃんの世話で精いっぱい、などさまざまな理由で「する気が起きない」という妻が多く、3か月から半年程度経ってから再開する人が多いようです。
また、授乳していると半年から1年で、授乳していない場合だと2か月から半年で生理が戻ってきます。産後、最初の方の生理では排卵がないことが多いといわれますが、徐々に排卵するようになるので生理があれば妊娠の可能性には気を留めておきましょう。
4. 夫の育児参加が、その後の長い夫婦生活を決める
夫の中には子どもを守って育てていく、子ども中心の生活にシフトしていくのだ、という自覚がなかなか持てない人もいるようです。妻が自分をかまってくれないと不満に思う(子育てに主体性を持てていない証です)、子どもがいない時と同じように時間やお金を飲み会や趣味に費やす(妻の不公平感、不満が蓄積します)、もっともひどい場合は浮気(損なった信頼は取り戻せません)。
産後クライシスを知っていますか
産後の心身の疲れや慣れない育児への不安や寝不足、昼間は子どもと二人だけになる生活のストレス、母乳によるホルモンバランスの変化などもあり、女性は過敏になっていたり、攻撃的になりやすくなっています。夫婦の関係やライフスタイルも出産前とは大きく変わっていき、夫の態度や行動によっては「産後クライシス」(出産後急激に夫婦仲が悪化すること)を引き起こす可能性もあります。
出産から乳児期の育児を夫婦でどれだけ協力してやったかどうかによって、妻の夫への愛情に変化があり、その後の長い夫婦生活を決める、というデータがあります(※)。この時期に「夫と二人で子育てした」と回答した妻の夫への愛情は、子どもが小学生から思春期へと成長していくのにつれて回復、維持されていきます。しかし、「自分一人で子育てした」と回答した妻の愛情は低いまま、もっと極端な場合は愛情がなくなっていきます。
ひたすら体力・気力が要る幼児期、心身ともに大きく成長していく小学生期、不機嫌が通常モードですべてに口答えをするようになる反抗期…。産後から乳児期の子育てに夫がどれだけ関われるかは、その後の子育てにおける土台にもなっていきます。
夫がもつべき「知識」
出産自体は妻がするものですが、まず夫に必要なのは妻の体や心に来される変化についての「知識」と、この時期の夫の出方が将来の夫婦生活にも多大な影響を与えるという「知識」です。その知識があることで、妻の状況を深く理解できるはずですし、夫自身、状況にふりまわされずに冷静に対処できるでしょう。夫としてなすべきこともみえてくるはずです。夫が「お手伝いレベル」ではなく赤ちゃんのケアをして一緒に過ごすこと、一通りの家事を夫一人で完結できること、これらが妻を、そして夫婦関係を救います。
5. 産後うつかも?のときの相談先
不安や不眠、落ち込みが強い場合には、躊躇しないで早めに市区町村の保健センターや医療機関に相談をするようにしましょう。
出産して間もない場合は、出産した病院での一か月健診で相談するのも手です。他にも子どもの6か月健診、1歳健診、1歳半健診や歯科健診などの機会にも保健師や臨床心理士に話をする機会がありますのでタイミングが近ければその時相談しましょう。もちろんタイミングに関わらず、保健センターや産後ケアセンター、各自治体の助産師会、出産した病院や子どもがかかっている病院など、いつでも相談できる相談先は様々存在します。早めに相談しましょう。
夫も相談を
夫側も困ったときには相談することが大事です。妻が産後うつや産後うつ気味の時どのように接したらいいのか、乳幼児の世話は具体的にどのようにするのか、自分には何ができるのか、夫も相談できます。夫が産後うつになることもあります。とくに、はじめての子どもケアは戸惑うことばかり、心配なことばかり、ということもあるでしょう。2人目、3人目の子どもでも、子どもによって性格や性質は違いますし、子どもが複数になるとより忙しく余裕がなくなってきて親が精神的に追いつめられるケースもあります。以下の相談先には、妊婦や産後、子育て中の女性だけではなく、夫婦の相談も含みますのでパートナーである夫ももちろん相談することができます。
産後うつや育児の悩みの相談先
まずは母体や赤ちゃんの様子を把握している病院に相談しましょう。通常窓口とは別に母子支援の電話番号やLINE相談を開設しているところもあります。
地方自治体が運営する相談先としてはお住まいの市区町村の保健センターがあげられます。保健センターでは乳幼児健診の運営・実施や、育児のための様々なサポート事業が行われています。保健センターの連絡先は母子手帳(おやこ手帳)にも記載されています。
厚生労働省の旗振りのもと、全国で「子育て世代包括支援センター」の設置が進められています。これは妊娠・出産・育児まで、ワンストップで親子をサポートする目的の地域拠点です。保健師・助産師等が、妊娠・出産・子育てに関する相談を電話・来所面接・家庭訪問等で行っています。未設置の市区町村もありますが、「子育て世代包括支援センター+自治体名」で検索してみてください。
各地の「日本助産師会」が相談窓口を設けている場合があります。自分が住んでいる自治体の助産師会の相談先は以下、または「住んでいる自治体名+助産師会」で検索してみてください。
日本助産師会/全国の相談窓口(外部リンク)
精神保健福祉センターは精神保健福祉法によって、各都道府県に設置することが定められている公的な機関です。心の問題や病気で困っているご本人や家族、関係者からの相談を受け、助言や専門の医療機関または相談機関に関する情報を提供しています。匿名での相談も可能です。
精神保健福祉センター(外部リンク)
特定非営利活動法人東京メンタルヘルス・スクエアが運営しているカウンセリング情報サイトです。誰でも利用できる無料の電話悩み相談(20分)「こころのほっとライン」やLINE、Twitter、Facebook、WEBチャットを使用したチャット形式でのSNS相談が可能です。
NPO法人東京メンタルヘルス・スクエア(外部リンク)
医療機関では精神科または心療内科を受診しましょう。いきなり精神科ということにハードルがあれば、まずはかかりつけの産婦人科に相談する方法もあります。その他、1~5にあげた相談窓口で適切な医療機関を紹介してもらうことも可能です。
産後うつになる前に!産後のサポートはまず地方自治体の事業を調べる
産後に手助けしてくれる人がいない、体調や赤ちゃんの世話が不安といった悩みは、ぎりぎりになるまで我慢せず、産後うつになる前に対策を講じることも重要です。
妊娠・出産・子育てに関する相談、支援の内容は市区町村によって様々な産後のケア事業・サービスがあり異なります。産前に申し込みが必要だったり、有料だったりするものもありますが、まずはお住まいの市区町村の情報を調べてみましょう。
自宅訪問事業
産後の母子のケアの一環として、保健師や助産師または看護師の自宅訪問事業を実施ししている市区町村が多くあります。出かけるのが難しいでも無料で自宅まで来てくれて相談にのってくれますので、悩み事などがあれば遠慮なく来てもらうようにしましょう。お住まいの市区町村にお問い合わせください。
宿泊・日帰りのケアサービス
子どもと一緒に、宿泊か日帰りの産後ケアサービスを提供する「産後ケア事業」を展開している市区町村もあります。実施しているところでは有料の場合が多いようですが、「産後ケア事業+(市区町村名)」などで検索してみましょう。
産後ケア事業/東京都世田谷区(外部リンク)
ヘルパー派遣
妊娠中・育児中の家事や育児のサポートを支援している自治体もあります。利用の可否や料金は世帯収入にもよりますが、お住いの市区町村で類似の支援事業がないか調べてみましょう。
産前産後ヘルパー派遣事業/横浜市(外部リンク)
情報収集・窓口は
まずはお住まいの市区町村役場に電話で問い合わせをしましょう。あらかじめ担当課がわからなくても、代表電話で「子育てのことで相談したい」などと伝えれば担当課につないでくれます。メールでの問い合わせ窓口のある市区町村もあるのでホームページを確認してみましょう。
また、先に産後うつや育児の悩みの相談先の1つとしても挙げた子育て世代包括支援センターがお住まいの市区町村にあればそちらでも情報が得られるはずです。「子育て世代包括支援センター+市区町村名」などで検索してみましょう。